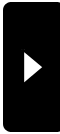2010年06月04日
戦闘機械としての銀河鉄道999号
ここまでに、実在する特急用蒸気機関車であるC62形と、アニメ世界の中で走る銀河超特急999号との相似点についてお話してきました。
ここでは銀河超特急が松本零士さんのワールドにある車輌であることを証明する「武装車輌」について、お話したいと思います。
現実世界の鉄道には装甲車輌は存在しませんし、大井川鉄道でイベント運行した999号にももちろん装甲車輌は編成されていませんでした。
アニメの中で、武装した車輌は銀河鉄道の戦闘力となります。
999号の1両としてつながれているものや独立して銀河鉄道から派遣されるものなどがありますが、ここでは3つの装甲車輌を紹介します。
●装甲車
999号の3両目に特別編成された装甲車で、それ自体が意思を持つ戦闘機械です。
命中すると相手を構成する物質を崩壊・消滅させてしまう凄まじい威力を持ったブラックホール砲を12門構えています。
第22話の「海賊船クイーンエメラルダス」で登場します。
●無軌道強行突破装甲車
これは999号に編成されたものではなく、他の星(鉄郎らが乗る客車が強制着陸させられた)を武力制圧するために秘密基地格納庫から発進したものです。
第38話「卑怯者の長老帝国」で登場します。
●鉄道警備隊装甲列車
反乱を起こして客車から離れてしまった999号の状況調査と、555号の郵便車を襲った強盗犯を捕まえるために派遣されました。
第69話「C62の反乱」で登場します。
もし大井川鉄道でのイベント用に装甲車輌が用意されていても、宇宙で戦うために造られたこれらの車輌は大井川沿線の風景にはきっとミスマッチだったでしょうね。
ここでは銀河超特急が松本零士さんのワールドにある車輌であることを証明する「武装車輌」について、お話したいと思います。
現実世界の鉄道には装甲車輌は存在しませんし、大井川鉄道でイベント運行した999号にももちろん装甲車輌は編成されていませんでした。
アニメの中で、武装した車輌は銀河鉄道の戦闘力となります。
999号の1両としてつながれているものや独立して銀河鉄道から派遣されるものなどがありますが、ここでは3つの装甲車輌を紹介します。
●装甲車
999号の3両目に特別編成された装甲車で、それ自体が意思を持つ戦闘機械です。
命中すると相手を構成する物質を崩壊・消滅させてしまう凄まじい威力を持ったブラックホール砲を12門構えています。
第22話の「海賊船クイーンエメラルダス」で登場します。
●無軌道強行突破装甲車
これは999号に編成されたものではなく、他の星(鉄郎らが乗る客車が強制着陸させられた)を武力制圧するために秘密基地格納庫から発進したものです。
第38話「卑怯者の長老帝国」で登場します。
●鉄道警備隊装甲列車
反乱を起こして客車から離れてしまった999号の状況調査と、555号の郵便車を襲った強盗犯を捕まえるために派遣されました。
第69話「C62の反乱」で登場します。
もし大井川鉄道でのイベント用に装甲車輌が用意されていても、宇宙で戦うために造られたこれらの車輌は大井川沿線の風景にはきっとミスマッチだったでしょうね。
2010年06月04日
銀河鉄道の厳しい規則
999の日に静岡県にある大井川鉄道で、銀河超特急999号が特別運行しました。
「999」のヘッドマークを付けた蒸気機関車、メーテルや車掌さんの登場、停車駅には銀河鉄道999に出てくる駅名と同じ看板を付けるなど、徹底してアニメの世界を再現し、乗客も銀河鉄道ワールドに引き込まれていたようです。
乗客自身が著名したパスを持っていなければ乗車できない、という規則もアニメそのままで、大井川鉄道を走った銀河超特急でも同じ方法がとられました。
さてこのパスの件のように、銀河鉄道には厳しい規則がいろいろあります。
999号に限らず、全ての列車において、運行の正確性や乗客と乗務員の罰則、敵への対応など、多岐にわたる項目があるようです。
どんな規則があるのか、その一部を見ていきたいと思います。
「銀河鉄道の列車の進行を妨害した者は、どんな理由があったとしても死刑とする」
「どんな状況においても、乗務員は乗客の安全に対して最善の努力を尽くす、万が一乗務員のミスにより乗客が死亡した場合は乗務員の死をもって償うこととする」
このように、死をもって償うといった項目もあり、これが「銀河鉄道規則は厳しい」と言われる所以です。
他には「乗客は列車の発車時刻に遅れた場合は置き去りにされ、さらにその乗客は以後、列車に乗ることは二度とできない」
「乗客は一度乗車したら、終点に着くまで途中下車はできない(指定施設への宿泊はこれに含まれない)」
など乗客に対する厳しい規則もあります。
実際にこれらの規則文書があるわけではないので、あくまでアニメの中の台詞や資料からの推測になりますが、かなり厳しい掟が存在することは確かなようです。
私たちが普段利用している鉄道と比較してみるのも面白いですよ。
銀河鉄道には「列車内で乗客が紛失した物があった場合、まったく同じ物を立て替えてもらえる」という決まりもあるようで、これが現実だったら鉄道会社は大赤字だなぁと考えたりもします。
「999」のヘッドマークを付けた蒸気機関車、メーテルや車掌さんの登場、停車駅には銀河鉄道999に出てくる駅名と同じ看板を付けるなど、徹底してアニメの世界を再現し、乗客も銀河鉄道ワールドに引き込まれていたようです。
乗客自身が著名したパスを持っていなければ乗車できない、という規則もアニメそのままで、大井川鉄道を走った銀河超特急でも同じ方法がとられました。
さてこのパスの件のように、銀河鉄道には厳しい規則がいろいろあります。
999号に限らず、全ての列車において、運行の正確性や乗客と乗務員の罰則、敵への対応など、多岐にわたる項目があるようです。
どんな規則があるのか、その一部を見ていきたいと思います。
「銀河鉄道の列車の進行を妨害した者は、どんな理由があったとしても死刑とする」
「どんな状況においても、乗務員は乗客の安全に対して最善の努力を尽くす、万が一乗務員のミスにより乗客が死亡した場合は乗務員の死をもって償うこととする」
このように、死をもって償うといった項目もあり、これが「銀河鉄道規則は厳しい」と言われる所以です。
他には「乗客は列車の発車時刻に遅れた場合は置き去りにされ、さらにその乗客は以後、列車に乗ることは二度とできない」
「乗客は一度乗車したら、終点に着くまで途中下車はできない(指定施設への宿泊はこれに含まれない)」
など乗客に対する厳しい規則もあります。
実際にこれらの規則文書があるわけではないので、あくまでアニメの中の台詞や資料からの推測になりますが、かなり厳しい掟が存在することは確かなようです。
私たちが普段利用している鉄道と比較してみるのも面白いですよ。
銀河鉄道には「列車内で乗客が紛失した物があった場合、まったく同じ物を立て替えてもらえる」という決まりもあるようで、これが現実だったら鉄道会社は大赤字だなぁと考えたりもします。
Posted by 関 at
17:44
│アニメの銀河鉄道999号について
2010年05月03日
銀河超特急999号が牽引する客車
2009年9月9日に大井川鉄道を銀河超特急999号が走り、たくさんのファンがカメラを持って集まりました。
この日はSLファンだけでなく、幼い頃からテレビで銀河鉄道999を見ていたというアニメファンも多く、中には「999」のナンバーをつけた自家用車で訪れた人もいたようです。
SLファン、アニメファンのどちらにとっても気になるのが、銀河超特急999号のモデル車輌ではないでしょうか。
銀河超特急がC62形をモデルとしていることは前にお話しましたが、ここでは機関車が牽引している客車について見ていきたいと思います。
まず外観では、結論から言うとアニメの中で描かれている客車は毎回同じ形状ではないため、特定するのが難しいのです。
しかしテレビ版でアップになったとき、車輌の両端にドアがある両デッキの、車体前後屋根の側面形状が直角になっている切妻車体が比較的多いようです。
そのためモデル客車はスハ43系、スハフ42系と考えることができます。
車体の色はアニメでは茶色で描かれていますが、スハ43系、スハフ42系には青色と茶色があり、青色率が80%と実際は茶色の車体は少ないようです。
次に客車の内部を見てみましょう。
マンガの中に出てくる客車内部は、2段式の木製サッシ窓、窓に垂直に交わるクロスシートでしたが、このようなタイプの客車は実在しないようです。
しかしアニメ版では1段式木製サッシの窓が描かれており、このことからスハ43系の客車ではないかと考えられます。
またオハ36系も木製枠にグリーンのクロスシートという座席で、内部は実にそれらしい形状をしています。
オハ36系は大井川鉄道に保存されています。
この日はSLファンだけでなく、幼い頃からテレビで銀河鉄道999を見ていたというアニメファンも多く、中には「999」のナンバーをつけた自家用車で訪れた人もいたようです。
SLファン、アニメファンのどちらにとっても気になるのが、銀河超特急999号のモデル車輌ではないでしょうか。
銀河超特急がC62形をモデルとしていることは前にお話しましたが、ここでは機関車が牽引している客車について見ていきたいと思います。
まず外観では、結論から言うとアニメの中で描かれている客車は毎回同じ形状ではないため、特定するのが難しいのです。
しかしテレビ版でアップになったとき、車輌の両端にドアがある両デッキの、車体前後屋根の側面形状が直角になっている切妻車体が比較的多いようです。
そのためモデル客車はスハ43系、スハフ42系と考えることができます。
車体の色はアニメでは茶色で描かれていますが、スハ43系、スハフ42系には青色と茶色があり、青色率が80%と実際は茶色の車体は少ないようです。
次に客車の内部を見てみましょう。
マンガの中に出てくる客車内部は、2段式の木製サッシ窓、窓に垂直に交わるクロスシートでしたが、このようなタイプの客車は実在しないようです。
しかしアニメ版では1段式木製サッシの窓が描かれており、このことからスハ43系の客車ではないかと考えられます。
またオハ36系も木製枠にグリーンのクロスシートという座席で、内部は実にそれらしい形状をしています。
オハ36系は大井川鉄道に保存されています。
Posted by 関 at
22:02
│銀河超特急999号について
2010年04月30日
C62形機関車と銀河超特急999号の共通点
これまでSLの走る大井川鉄道にスポットを当ててお話してきましたが、ここからはアニメ「銀河鉄道999」の世界も見ていきたいと思います。
2009年9月9日、大井川鉄道を銀河超特急999号特別列車が走った時は、多くのSLファンとアニメファンが訪れたそうで、未だ銀河鉄道999が根強い人気を誇っていることが伺えました。
アニメファン、SLファンのほとんどの人は、銀河超特急999号が実在するC62形機関車をモデルとして描かれたことを知っているでしょう。
しかし、いくらモデルにしたとは言え、実在の機関車とアニメの世界に描かれる機関車が全く同じというわけではありません。
ここでは現存しているC62形機関車と、アニメ中に出てくる銀河超特急との相似点を挙げてみます。
ナンバープレートについては後ほど詳しくお話しますが、原作と劇場版ではC62-48、テレビ版ではC62-50となっています。
実在する機関車はC62形49号機までです。
次にC62形のキャブ部についてですが、実際に造られた49両それぞれに微妙な違いがあるため、どれがアニメのモデルとなったのか特定が難しいところです。
蒸気機関車は走らせる地域で使いやすくするため改造が加えられていきます。
それで同じように造られた機関車でも段々違いが出てくるのです。
車輌を特定する場合、キャブ後部にあるひさしのカーブや雨どいを見て判断するのですが、そもそも999号は屋根のひさしが短すぎるためモデル車輌を特定することはできません。
次に砂をまくための管ですが、銀河超特急ではこの砂まき管が3本、ボイラー外皮に直線的につながっています。
このような配置は実際のC62形には見られず、おそらくデフォルメされたものなのでしょう。
近いイメージとしてはC62形1号機がありますが、こちらは当初2本の砂まき管だったものを改造して3本にした車輌です。
このように実存するモデル車輌を特定できそうでできない、この葛藤がまた銀河鉄道999の面白さのひとつでもあるようです。
2009年9月9日、大井川鉄道を銀河超特急999号特別列車が走った時は、多くのSLファンとアニメファンが訪れたそうで、未だ銀河鉄道999が根強い人気を誇っていることが伺えました。
アニメファン、SLファンのほとんどの人は、銀河超特急999号が実在するC62形機関車をモデルとして描かれたことを知っているでしょう。
しかし、いくらモデルにしたとは言え、実在の機関車とアニメの世界に描かれる機関車が全く同じというわけではありません。
ここでは現存しているC62形機関車と、アニメ中に出てくる銀河超特急との相似点を挙げてみます。
ナンバープレートについては後ほど詳しくお話しますが、原作と劇場版ではC62-48、テレビ版ではC62-50となっています。
実在する機関車はC62形49号機までです。
次にC62形のキャブ部についてですが、実際に造られた49両それぞれに微妙な違いがあるため、どれがアニメのモデルとなったのか特定が難しいところです。
蒸気機関車は走らせる地域で使いやすくするため改造が加えられていきます。
それで同じように造られた機関車でも段々違いが出てくるのです。
車輌を特定する場合、キャブ後部にあるひさしのカーブや雨どいを見て判断するのですが、そもそも999号は屋根のひさしが短すぎるためモデル車輌を特定することはできません。
次に砂をまくための管ですが、銀河超特急ではこの砂まき管が3本、ボイラー外皮に直線的につながっています。
このような配置は実際のC62形には見られず、おそらくデフォルメされたものなのでしょう。
近いイメージとしてはC62形1号機がありますが、こちらは当初2本の砂まき管だったものを改造して3本にした車輌です。
このように実存するモデル車輌を特定できそうでできない、この葛藤がまた銀河鉄道999の面白さのひとつでもあるようです。
2010年04月28日
銀河超特急のナンバープレート物語
アニメや映画で幅広い年齢の人から人気を得ている銀河鉄道999に登場する銀河超特急999号が、実はC62形という実在の蒸気機関車をモデルにしているのはよく知られた話です。
銀河鉄道に蒸気機関車を選んだことで、物語の中に旅愁の深みが出ているように感じます。
テレビで見ていた頃、流れてくるエンディングソングと画面に映る銀河超特急999号が子供心にも妙に切なかったことが思い出されます。
9がぞろ目で揃う999の日(9月9日)に大井川鉄道で銀河超特急が走るという記念イベントが行なわれましたが、この日999号として走ったのはC11形でした。
銀河超特急のモデルとなったのはC62形ですから、テレビで見る999号のナンバープレートは「C62-50」となっています。
(ちなみに大井川鉄道で走った999号のナンバープレートはC11-190でした。)
実際のC62形は49台しか製造されなかったため、テレビ放送では実在しないC62-50というナンバーを使用したのです。
しかし原作と劇場版では「C62-48」のナンバープレートをつけた999号が走っているのです。
なぜ劇場版では原作のようにC62-48のナンバープレートを描くことができたのでしょうか。
これには諸説ありますが、C62-50で描いたテレビ版が放送されている時に、当時の国鉄がアニメの作者である松本零士さんにC62-48のプレートを進呈したため、という説が有力なようです。
私も子ども時代にはナンバープレートの数字まで考えてテレビを見ていませんでしたが、大人になって改めて細部まで見てみると、このようにアニメとは別のところの動きが見えてきて興味深いです。
銀河鉄道に蒸気機関車を選んだことで、物語の中に旅愁の深みが出ているように感じます。
テレビで見ていた頃、流れてくるエンディングソングと画面に映る銀河超特急999号が子供心にも妙に切なかったことが思い出されます。
9がぞろ目で揃う999の日(9月9日)に大井川鉄道で銀河超特急が走るという記念イベントが行なわれましたが、この日999号として走ったのはC11形でした。
銀河超特急のモデルとなったのはC62形ですから、テレビで見る999号のナンバープレートは「C62-50」となっています。
(ちなみに大井川鉄道で走った999号のナンバープレートはC11-190でした。)
実際のC62形は49台しか製造されなかったため、テレビ放送では実在しないC62-50というナンバーを使用したのです。
しかし原作と劇場版では「C62-48」のナンバープレートをつけた999号が走っているのです。
なぜ劇場版では原作のようにC62-48のナンバープレートを描くことができたのでしょうか。
これには諸説ありますが、C62-50で描いたテレビ版が放送されている時に、当時の国鉄がアニメの作者である松本零士さんにC62-48のプレートを進呈したため、という説が有力なようです。
私も子ども時代にはナンバープレートの数字まで考えてテレビを見ていませんでしたが、大人になって改めて細部まで見てみると、このようにアニメとは別のところの動きが見えてきて興味深いです。
Posted by 関 at
19:21
│銀河超特急のナンバープレート
2010年04月24日
大井川鉄道沿線の見所
大井川鉄道を普通列車でのんびり旅するのもよいものですが、SLに乗りたくて大井川鉄道を訪れる人も多いと思います。
2009年秋に行なわれた銀河超特急999号のイベント運行で初めて大井川鉄道を訪れた人もいるかもしれませんね。
銀河超特急999号もそうでしたが、SL列車は急行なので各駅停車ではありません。
金谷駅を出発してから終点の千頭駅に到着するまでに停車する駅は、新金谷駅、家山駅、下泉駅、駿河徳山駅です。
千頭駅発のSLは、加えて笹間渡駅にも停車します。
ここではSLが停車する駅から立ち寄れるいくつかのスポットを紹介します。
まず始発駅となる金谷駅、ここから国道473号線沿いに牧之原方面に5分ほど歩くと、旧東海道金谷坂石畳へ行くことができます。
ここは江戸時代に東海道の難所として名を知られた金谷坂で、平成3年に金谷町民約600名の参加によって復元された石畳です。
竹や杉の木がトンネルを作る430mの石畳を歩いていると、当時の旅人の苦労が偲ばれます。
石畳の入口にある数寄屋造りの石畳茶屋では、地元の金谷茶を囲炉裏端で味わうことができます。
次に家山駅ですが、桜の季節に訪れたらぜひ家山の桜トンネルを見物してください。
大井川鉄道に沿った県道の両側に500本もの桜が植えられ、3月終わりから4月にかけて一斉に花開く様はとても素晴らしいものです。
その脇をSLが駆け抜けて行く光景は、旅の思い出として忘れられないものとなるでしょう。
また家山駅前にあるお茶の朝日園が手がけるお茶専門の喫茶店「遊」にもぜひ立ち寄ってみてください。
茶房「遊」では香りの良い川根茶だけでなく、川根産の中国茶や紅茶も味わうことができます。
お茶を使ったスイーツも楽しめますよ。
駿河徳山駅からは徒歩10分で行ける「フォーレなかかわね茶茗館」を紹介します。
ここでは川根茶に関する歴史や栽培方法、お茶と健康の関わりなどが学べます。
入館は無料で、川根茶とお茶菓子が300円でいただけます。
やはりお茶処静岡なだけに、地元のお茶を楽しめるスポットが多く感じます。
SLとお茶、これもまた旅愁を誘う組み合わせですね。
2009年秋に行なわれた銀河超特急999号のイベント運行で初めて大井川鉄道を訪れた人もいるかもしれませんね。
銀河超特急999号もそうでしたが、SL列車は急行なので各駅停車ではありません。
金谷駅を出発してから終点の千頭駅に到着するまでに停車する駅は、新金谷駅、家山駅、下泉駅、駿河徳山駅です。
千頭駅発のSLは、加えて笹間渡駅にも停車します。
ここではSLが停車する駅から立ち寄れるいくつかのスポットを紹介します。
まず始発駅となる金谷駅、ここから国道473号線沿いに牧之原方面に5分ほど歩くと、旧東海道金谷坂石畳へ行くことができます。
ここは江戸時代に東海道の難所として名を知られた金谷坂で、平成3年に金谷町民約600名の参加によって復元された石畳です。
竹や杉の木がトンネルを作る430mの石畳を歩いていると、当時の旅人の苦労が偲ばれます。
石畳の入口にある数寄屋造りの石畳茶屋では、地元の金谷茶を囲炉裏端で味わうことができます。
次に家山駅ですが、桜の季節に訪れたらぜひ家山の桜トンネルを見物してください。
大井川鉄道に沿った県道の両側に500本もの桜が植えられ、3月終わりから4月にかけて一斉に花開く様はとても素晴らしいものです。
その脇をSLが駆け抜けて行く光景は、旅の思い出として忘れられないものとなるでしょう。
また家山駅前にあるお茶の朝日園が手がけるお茶専門の喫茶店「遊」にもぜひ立ち寄ってみてください。
茶房「遊」では香りの良い川根茶だけでなく、川根産の中国茶や紅茶も味わうことができます。
お茶を使ったスイーツも楽しめますよ。
駿河徳山駅からは徒歩10分で行ける「フォーレなかかわね茶茗館」を紹介します。
ここでは川根茶に関する歴史や栽培方法、お茶と健康の関わりなどが学べます。
入館は無料で、川根茶とお茶菓子が300円でいただけます。
やはりお茶処静岡なだけに、地元のお茶を楽しめるスポットが多く感じます。
SLとお茶、これもまた旅愁を誘う組み合わせですね。
2010年04月22日
戦争に巻き込まれるC56形機関車
大井川鉄道にはC10形、C11形、C12形、C56形などのSLが今でも元気に走っています。
平成7年7月7日には千頭駅に7両の蒸気機関車が揃ってお目見えしたり、2009年9月9日には銀河超特急999号が走ったりと、ぞろ目の日などにイベントが行なわれています。
銀河超特急はC11形の1両だけが999号として特別運行しましたが、やはりいろいろなイベントが開催できるのも、保存車輌数が多い大井川鉄道なればこそです。
これらのSLはそれぞれに大井川鉄道とは違う場所での歴史を持ってやって来たのですが、中でも大変な歴史を持つC56形蒸気機関車について、ここではお話したいと思います。
ポニーと呼ばれるC56形機関車は、第二次世界大戦の間、タイやビルマに送られ、戦争のために働いていたのです。
C56形が走っていたのはタイメン鉄道というタイからビルマへ軍隊を送るための鉄道でした。
タイメン鉄道はわずか1年3ヶ月の期間で急いで作られた415kmもの長い鉄道です。
人が入ったこともないようなジャングル、深い谷、山々…そんな過酷な場所に鉄道を敷くのは、容易なことではありません。
猛獣や毒ヘビ、サソリなどの危険生物、マラリアなどの恐ろしい病気、そして敵からの爆撃など、多くの犠牲者を出しながら強引に工事が進められました。
その末に完成した鉄道は、ただ地面を平らにして枕木を敷き、レールを乗せ、谷川には木を積んで架けた橋にレールを乗せただけという簡易的なものでした。
重い列車が通ると当然ながら路線が沈んでしまったり、雨が続くとすぐに流されることもありました。
日本からやって来たC56形機関車はこのタイメン鉄道で多くの兵隊や食料、弾薬を積んで走りました。
脱線や転覆、時には橋が崩れて谷底へ落ちて行くこともありました。
そんな悪条件の中でも、C56形は懸命に走り続けたのです。
戦争が終わって日本に帰って来たのは、たった2両となってしまいました。
そのうちの1両が、現在、大井川鉄道で煙を上げるC56形44号機なのです。
今日もC56形は、昔のつらい思い出を抱えながら、今は平和となった大井川に沿って走っています。
平成7年7月7日には千頭駅に7両の蒸気機関車が揃ってお目見えしたり、2009年9月9日には銀河超特急999号が走ったりと、ぞろ目の日などにイベントが行なわれています。
銀河超特急はC11形の1両だけが999号として特別運行しましたが、やはりいろいろなイベントが開催できるのも、保存車輌数が多い大井川鉄道なればこそです。
これらのSLはそれぞれに大井川鉄道とは違う場所での歴史を持ってやって来たのですが、中でも大変な歴史を持つC56形蒸気機関車について、ここではお話したいと思います。
ポニーと呼ばれるC56形機関車は、第二次世界大戦の間、タイやビルマに送られ、戦争のために働いていたのです。
C56形が走っていたのはタイメン鉄道というタイからビルマへ軍隊を送るための鉄道でした。
タイメン鉄道はわずか1年3ヶ月の期間で急いで作られた415kmもの長い鉄道です。
人が入ったこともないようなジャングル、深い谷、山々…そんな過酷な場所に鉄道を敷くのは、容易なことではありません。
猛獣や毒ヘビ、サソリなどの危険生物、マラリアなどの恐ろしい病気、そして敵からの爆撃など、多くの犠牲者を出しながら強引に工事が進められました。
その末に完成した鉄道は、ただ地面を平らにして枕木を敷き、レールを乗せ、谷川には木を積んで架けた橋にレールを乗せただけという簡易的なものでした。
重い列車が通ると当然ながら路線が沈んでしまったり、雨が続くとすぐに流されることもありました。
日本からやって来たC56形機関車はこのタイメン鉄道で多くの兵隊や食料、弾薬を積んで走りました。
脱線や転覆、時には橋が崩れて谷底へ落ちて行くこともありました。
そんな悪条件の中でも、C56形は懸命に走り続けたのです。
戦争が終わって日本に帰って来たのは、たった2両となってしまいました。
そのうちの1両が、現在、大井川鉄道で煙を上げるC56形44号機なのです。
今日もC56形は、昔のつらい思い出を抱えながら、今は平和となった大井川に沿って走っています。
2010年04月18日
鉄道沿線の露天風呂でSLを眺める
銀河鉄道999が公開されて30年、大井川鉄道では特別列車として「銀河超特急999号」が運行しました。
新金谷駅の99番(特設)ホームを出発、終点千頭駅改め惑星プロメシュームを目指して走る銀河超特急には、アニメファンや鉄道ファン約360人が乗車していました。
アニメの世界にいるような本格的な999号と様々な演出に、多くの乗客が感激していたようです。
しかし、煙を上げ、郷愁を感じさせる汽笛を鳴らして走るSLの雄姿に胸を躍らせるのは、SLファンばかりではありません。
そんなに鉄道に詳しくない人や子どもにとっても、そんなSLの姿は胸の高鳴りを誘うものです。
大井川鉄道沿線には、SLを間近に見られる興奮を味わいながら露天風呂に浸かれるという贅沢な場所があります。
それが笹間渡駅から徒歩5分のところにある「川根温泉ふれあいの泉」です。
ここの露天風呂では、目の前にある大井川にかかる鉄橋を、SLが豪快に駆けていく姿が見られます。
あっという間の眺めですが、温泉に浸かりながら体も心も温まる体験ができることでしょう。
源泉かけ流しの温泉は、露天風呂の他に檜風呂や炭風呂などもあり、湯量豊富な川根温泉をじっくり楽しむことができます。
川根温泉ふれあいの泉の営業時間は朝9時から夜9時まで、休館日は毎月第一火曜日です。
利用料金は、大人が入浴500円、プール700円、共通1000円、小学生が入浴300円、プール300円、共通500円となっています。
アクセスで注意しておきたいことは、金谷駅を出発する下りのSLは笹間渡駅に停車しないので、普通列車を利用しなければならないことです。
千頭駅を出発する上りのSLは笹間渡駅にも停車します。
新金谷駅の99番(特設)ホームを出発、終点千頭駅改め惑星プロメシュームを目指して走る銀河超特急には、アニメファンや鉄道ファン約360人が乗車していました。
アニメの世界にいるような本格的な999号と様々な演出に、多くの乗客が感激していたようです。
しかし、煙を上げ、郷愁を感じさせる汽笛を鳴らして走るSLの雄姿に胸を躍らせるのは、SLファンばかりではありません。
そんなに鉄道に詳しくない人や子どもにとっても、そんなSLの姿は胸の高鳴りを誘うものです。
大井川鉄道沿線には、SLを間近に見られる興奮を味わいながら露天風呂に浸かれるという贅沢な場所があります。
それが笹間渡駅から徒歩5分のところにある「川根温泉ふれあいの泉」です。
ここの露天風呂では、目の前にある大井川にかかる鉄橋を、SLが豪快に駆けていく姿が見られます。
あっという間の眺めですが、温泉に浸かりながら体も心も温まる体験ができることでしょう。
源泉かけ流しの温泉は、露天風呂の他に檜風呂や炭風呂などもあり、湯量豊富な川根温泉をじっくり楽しむことができます。
川根温泉ふれあいの泉の営業時間は朝9時から夜9時まで、休館日は毎月第一火曜日です。
利用料金は、大人が入浴500円、プール700円、共通1000円、小学生が入浴300円、プール300円、共通500円となっています。
アクセスで注意しておきたいことは、金谷駅を出発する下りのSLは笹間渡駅に停車しないので、普通列車を利用しなければならないことです。
千頭駅を出発する上りのSLは笹間渡駅にも停車します。
2010年04月15日
工事用トロッコ軌道の井川線
銀河超特急999号が走ったことでも話題になりSLファンやアニメファンの関心を集めた大井川鉄道ですが、SLが走る大井川鉄道本線の先、さらに奥地へと向かう井川線についてはどのくらいの人が知っているのでしょうか。
鉄道全般に興味がある人は日本で唯一のアプト式鉄道としてよく知っているかもしれませんし、銀河超特急999号に乗車した人の中には終点の千頭駅からさらに奥へ伸びる路線に興味を持った人がいるかもしれません。
この井川線では、同じ大井川鉄道でも金谷駅~千頭駅の大井川本線とは異なった趣きを醸しています。
なぜなら、井川線はもともとダムや発電所を建設するために設置された工事用トロッコ軌道だからです。
車内では天井に手が届きそうなほどの小さな車輌が井川線を走ります。
井川線は奥大井の渓谷を走るため、蒸気機関車の車窓から見えた広大な大井川ではなく、断崖絶壁の下を流れる急流を目にすることになります。
寸又峡温泉への下車駅である奥泉駅を過ぎると、アプトいちしろ駅に到着します。
ここから先が、日本唯一と言われるアプト式鉄道です。
アプト式鉄道では、線路のレールの間にあるギザギザのラックレールと、アプト式機関車の車体下に取り付けられた歯車が噛み合いながら急勾配を上っていきます。
この勾配は、1000m水平に進む間に90m上昇するという日本一の急勾配です。
ピョーッという甲高いホイッスルはスイス国鉄から親善として贈られたもので、本場の登山汽笛を奏でてこの急勾配をグングン上っていきます。
大井川の水面があっと言う間にはるか眼下に遠ざかると、アプト式鉄道の力強さを改めて感じてしまうのです。
旅行を計画している人には紅葉や温泉やダム散策など見所も多い井川線の旅も、おすすめですよ。
鉄道全般に興味がある人は日本で唯一のアプト式鉄道としてよく知っているかもしれませんし、銀河超特急999号に乗車した人の中には終点の千頭駅からさらに奥へ伸びる路線に興味を持った人がいるかもしれません。
この井川線では、同じ大井川鉄道でも金谷駅~千頭駅の大井川本線とは異なった趣きを醸しています。
なぜなら、井川線はもともとダムや発電所を建設するために設置された工事用トロッコ軌道だからです。
車内では天井に手が届きそうなほどの小さな車輌が井川線を走ります。
井川線は奥大井の渓谷を走るため、蒸気機関車の車窓から見えた広大な大井川ではなく、断崖絶壁の下を流れる急流を目にすることになります。
寸又峡温泉への下車駅である奥泉駅を過ぎると、アプトいちしろ駅に到着します。
ここから先が、日本唯一と言われるアプト式鉄道です。
アプト式鉄道では、線路のレールの間にあるギザギザのラックレールと、アプト式機関車の車体下に取り付けられた歯車が噛み合いながら急勾配を上っていきます。
この勾配は、1000m水平に進む間に90m上昇するという日本一の急勾配です。
ピョーッという甲高いホイッスルはスイス国鉄から親善として贈られたもので、本場の登山汽笛を奏でてこの急勾配をグングン上っていきます。
大井川の水面があっと言う間にはるか眼下に遠ざかると、アプト式鉄道の力強さを改めて感じてしまうのです。
旅行を計画している人には紅葉や温泉やダム散策など見所も多い井川線の旅も、おすすめですよ。
Posted by 関 at
22:46
│銀河鉄道の井川線沿線
2010年04月12日
レトロな客車,999号が走る大井川鉄道SLの旅
大井川鉄道のSLは、こげ茶色をしたレトロな客車を連ねて走ります。
他の鉄道会社で走る蒸気機関車はモダンな展望車やカフェカーなどを繋いで走ることが多いのですが、大井川鉄道ではあくまでも「蒸気機関車は歴史的な文化遺産」との考えで、あえて客車を当時に近い形でそのまま走らせているのです。
銀河鉄道999の1作目公開から30年を記念して大井川鉄道を走った「銀河超特急999号」においても、ボックスシートの旧型客車と展望車の合わせて5両を編成していました。
銀河超特急は特別な列車だとは言っても、やはりレトロな客車が999号にはしっくり合っていたようです。
さて、大井川鉄道SLの旅を始発の金谷駅から始めることにしましょう。
旧型客車を連ねて蒸気機関車がホームに入って来たら、興奮して走り出すことのないよう気持ちを抑えながら乗車しましょう。
車内に入るとニス塗りの壁や板張りの床の、何とも言えない懐かしい香りに包まれます。
木枠の座席や天井の白熱灯、網棚など、昭和の古き良き時代にタイムスリップした気分になります。
(この気分を味わえるのは、ある程度の年齢を超えている人に限りますが…)
スピードや快適性を重視した現代の乗り物では味わえない、独特の趣きがそこにはあります。
「ボッボーーー」という懐かしい汽笛が聞こえたら、いよいよ出発です。
汽車ぽっぽという可愛らしい響きには聞こえない野太い汽笛も、旅への期待と共に郷愁の気持ちを起こさせます。
終点千頭駅までのおよそ1時間20分の道中、レトロなボックスシートに揺られながら、車窓に見える圧倒的な山並みと渓谷の美しさを楽しんでください。
他の鉄道会社で走る蒸気機関車はモダンな展望車やカフェカーなどを繋いで走ることが多いのですが、大井川鉄道ではあくまでも「蒸気機関車は歴史的な文化遺産」との考えで、あえて客車を当時に近い形でそのまま走らせているのです。
銀河鉄道999の1作目公開から30年を記念して大井川鉄道を走った「銀河超特急999号」においても、ボックスシートの旧型客車と展望車の合わせて5両を編成していました。
銀河超特急は特別な列車だとは言っても、やはりレトロな客車が999号にはしっくり合っていたようです。
さて、大井川鉄道SLの旅を始発の金谷駅から始めることにしましょう。
旧型客車を連ねて蒸気機関車がホームに入って来たら、興奮して走り出すことのないよう気持ちを抑えながら乗車しましょう。
車内に入るとニス塗りの壁や板張りの床の、何とも言えない懐かしい香りに包まれます。
木枠の座席や天井の白熱灯、網棚など、昭和の古き良き時代にタイムスリップした気分になります。
(この気分を味わえるのは、ある程度の年齢を超えている人に限りますが…)
スピードや快適性を重視した現代の乗り物では味わえない、独特の趣きがそこにはあります。
「ボッボーーー」という懐かしい汽笛が聞こえたら、いよいよ出発です。
汽車ぽっぽという可愛らしい響きには聞こえない野太い汽笛も、旅への期待と共に郷愁の気持ちを起こさせます。
終点千頭駅までのおよそ1時間20分の道中、レトロなボックスシートに揺られながら、車窓に見える圧倒的な山並みと渓谷の美しさを楽しんでください。
2010年04月11日
大井川鉄道は走る鉄道博物館
現在、SL運行している鉄道会社と聞くと、静岡県の大井川鉄道を思い浮かべる人も多いことでしょう。
銀河超特急999号としてイベント走行したC11形機関車も、普段から旧型客車を牽引し各地から訪れた大人や子どもを乗せて元気に走っています。
銀河超特急999号は「999」のマークを付けてアニメの姿さながらに走りましたが、大井川鉄道の上り列車は普段SLが反対向き(バック走行)で客車を牽引しています。
このように大井川鉄道ではSLの運行が有名ですが、一方で他社の路線でかつて華やかに活躍していた車輌がここへ移籍して第二の人生を歩んでいる場所でもあるのです。
各地から集められた列車が走る鉄道博物館といったところでしょうか。
ここでは大井川鉄道を走るかつての花形車輌から2つを紹介しましょう。
●南海21001系
ズームカーの愛称で呼ばれていた1958年生まれの南海21001系列車は、主に急行用に使われ繁忙期には特急として活躍していました。
一般的に高速性と登坂性能は相反するのですが、ズームカーにおいては平坦な路面を110km/時で走行しながら登山区間も力強く登れるという二面性を両立させました。
大井川鉄道に1994年にやって来て、高速性能を発揮できる場面はないものの、得意の登り場面で能力を発揮しています。
●近鉄1600系
この列車は吉野特急として近鉄南大阪線で活躍していました。
近鉄特急は通常の運賃の他に特急料金が必要な全車座席指定有料特急です。
そのためこの車輌は有料特急としての風格を持っており、急行以下の車輌とは差が見られます。
大井川鉄道に移籍した際、トイレなどの設備は撤去されましたが、それ以外はほぼそのままの形で使われています。
大井川鉄道を利用する一般の乗客は、このような格の高い車輌に普通運賃だけで乗れてしまうなんて、うらやましくもありますね。
銀河超特急999号としてイベント走行したC11形機関車も、普段から旧型客車を牽引し各地から訪れた大人や子どもを乗せて元気に走っています。
銀河超特急999号は「999」のマークを付けてアニメの姿さながらに走りましたが、大井川鉄道の上り列車は普段SLが反対向き(バック走行)で客車を牽引しています。
このように大井川鉄道ではSLの運行が有名ですが、一方で他社の路線でかつて華やかに活躍していた車輌がここへ移籍して第二の人生を歩んでいる場所でもあるのです。
各地から集められた列車が走る鉄道博物館といったところでしょうか。
ここでは大井川鉄道を走るかつての花形車輌から2つを紹介しましょう。
●南海21001系
ズームカーの愛称で呼ばれていた1958年生まれの南海21001系列車は、主に急行用に使われ繁忙期には特急として活躍していました。
一般的に高速性と登坂性能は相反するのですが、ズームカーにおいては平坦な路面を110km/時で走行しながら登山区間も力強く登れるという二面性を両立させました。
大井川鉄道に1994年にやって来て、高速性能を発揮できる場面はないものの、得意の登り場面で能力を発揮しています。
●近鉄1600系
この列車は吉野特急として近鉄南大阪線で活躍していました。
近鉄特急は通常の運賃の他に特急料金が必要な全車座席指定有料特急です。
そのためこの車輌は有料特急としての風格を持っており、急行以下の車輌とは差が見られます。
大井川鉄道に移籍した際、トイレなどの設備は撤去されましたが、それ以外はほぼそのままの形で使われています。
大井川鉄道を利用する一般の乗客は、このような格の高い車輌に普通運賃だけで乗れてしまうなんて、うらやましくもありますね。
2010年04月10日
大井川鉄道のダイヤで、蒸気機関車(SL)の旅
「子どもが汽車に乗りたいと言うので、夏休みに大井川鉄道に行ってきたよ」という話を友人がしていました。
大人には懐かしさを感じる蒸気機関車も、子どもにとっては機関車トーマスに乗るような新鮮なイメージがあるのかもしれません。
2009年9月には、銀河超特急999号の運行というアニメファンなら放っておけないイベントもありました。
昔から銀河鉄道999のアニメを見ていた人たちにとって、駅名やヘッドマークまでアニメの世界そのままの銀河超特急999号に乗ることはとても感慨深いものだったでしょう。
さて、大井川鉄道SLの旅についてお話をしましょう。
まず始発はJR東海道本線の金谷駅に隣接している大井川鉄道の金谷駅になります。
蒸気機関車は冬季に入る12月から3月中旬の火曜日、木曜日以外は毎日運行しています。
基本的には金谷駅を11:48発、千頭駅を15:23発(冬季は14:58発)のダイヤで毎日1往復しています。
桜の季節の週末や、夏休み、紅葉の季節は1日2往復(金谷駅10:02発・11:48発、千頭駅14:58発・15:23発)走っています。
さらにこれからの紅葉シーズンの週末には金谷駅11:07発、千頭駅14:16発も増えて1日3往復となります。
このように行楽シーズンに蒸気機関車の増発が可能であるのも、多くの機関車を動態保存している大井川鉄道なればこそ、なのです。
このダイヤなら、東京や大阪からでも朝の新幹線で訪れれば間に合いますし、都合で日帰り旅行しか計画できなくても十分SLの旅を楽しむことができます。
大人には懐かしさを感じる蒸気機関車も、子どもにとっては機関車トーマスに乗るような新鮮なイメージがあるのかもしれません。
2009年9月には、銀河超特急999号の運行というアニメファンなら放っておけないイベントもありました。
昔から銀河鉄道999のアニメを見ていた人たちにとって、駅名やヘッドマークまでアニメの世界そのままの銀河超特急999号に乗ることはとても感慨深いものだったでしょう。
さて、大井川鉄道SLの旅についてお話をしましょう。
まず始発はJR東海道本線の金谷駅に隣接している大井川鉄道の金谷駅になります。
蒸気機関車は冬季に入る12月から3月中旬の火曜日、木曜日以外は毎日運行しています。
基本的には金谷駅を11:48発、千頭駅を15:23発(冬季は14:58発)のダイヤで毎日1往復しています。
桜の季節の週末や、夏休み、紅葉の季節は1日2往復(金谷駅10:02発・11:48発、千頭駅14:58発・15:23発)走っています。
さらにこれからの紅葉シーズンの週末には金谷駅11:07発、千頭駅14:16発も増えて1日3往復となります。
このように行楽シーズンに蒸気機関車の増発が可能であるのも、多くの機関車を動態保存している大井川鉄道なればこそ、なのです。
このダイヤなら、東京や大阪からでも朝の新幹線で訪れれば間に合いますし、都合で日帰り旅行しか計画できなくても十分SLの旅を楽しむことができます。
2010年04月09日
蒸気機関車を動態保存する大井川鉄道
大井川鉄道は偉大なるローカル私鉄である、と一部のSLファンから言われています。
それは、蒸気機関車(SL)の保存運転という、JR各社や他の大きな鉄道会社では成し得なかった素晴らしい偉業を実現させたからです。
現在では各地でSLの復活運転がされるようになり、銀河超特急999号のイベント運行なども開催されていますが、中でも大井川鉄道は蒸気機関車保存に関するパイオニア的存在なのです。
ちなみに過去に銀河超特急999号のイベントは各地で行なわれましたが、9月9日当日に走らせたのは大井川鉄道が初めてだそうです。
今から40年近く昔のことになりますが、名古屋鉄道から一人の鉄道マンが大井川鉄道の副社長としてやって来ました。
副社長は就任するとすぐに徹底的な合理化を図り、様々な企画に関するアイデアも打ち出しました。
その一つが当時、すでに廃車が決まっていたイギリス生まれのB6形蒸気機関車の保存運転だったのです。
そしてこのB6形蒸気機関車の保存をきっかけに、蒸気機関車を歴史的な文化遺産であると位置づけ、積極的に動態保存することに努めてきました。
常に走行可能な状態で保存する動態保存は欧米国が熱心に取り組み、特にイギリスでは700両もの蒸気機関車が動態保存されているそうです。
日本の鉄道保存に対する意識の低さを感じてしまいますが、それゆえに大井川鉄道の取り組みは称賛されるべきだと思うのです。
動態保存に積極的な大井川鉄道には、海外から鉄道関係者が視察に訪れることもあるそうです。
それは、蒸気機関車(SL)の保存運転という、JR各社や他の大きな鉄道会社では成し得なかった素晴らしい偉業を実現させたからです。
現在では各地でSLの復活運転がされるようになり、銀河超特急999号のイベント運行なども開催されていますが、中でも大井川鉄道は蒸気機関車保存に関するパイオニア的存在なのです。
ちなみに過去に銀河超特急999号のイベントは各地で行なわれましたが、9月9日当日に走らせたのは大井川鉄道が初めてだそうです。
今から40年近く昔のことになりますが、名古屋鉄道から一人の鉄道マンが大井川鉄道の副社長としてやって来ました。
副社長は就任するとすぐに徹底的な合理化を図り、様々な企画に関するアイデアも打ち出しました。
その一つが当時、すでに廃車が決まっていたイギリス生まれのB6形蒸気機関車の保存運転だったのです。
そしてこのB6形蒸気機関車の保存をきっかけに、蒸気機関車を歴史的な文化遺産であると位置づけ、積極的に動態保存することに努めてきました。
常に走行可能な状態で保存する動態保存は欧米国が熱心に取り組み、特にイギリスでは700両もの蒸気機関車が動態保存されているそうです。
日本の鉄道保存に対する意識の低さを感じてしまいますが、それゆえに大井川鉄道の取り組みは称賛されるべきだと思うのです。
動態保存に積極的な大井川鉄道には、海外から鉄道関係者が視察に訪れることもあるそうです。
2010年04月08日
大井川鉄道が出来るまで
紅葉のきれいな季節、日本の四季の美しさをゆっくり堪能するのなら蒸気機関車での旅もおすすめです。
SLの旅に大井川鉄道を選ぶ人も多いと思います。
大井川鉄道では銀河超特急999号を走らせたことでも話題となりましたが、ここのSLは観光列車としても有名です。
大井川鉄道は、たくさんのSLを走らせる状態で保存する「動態保存」している鉄道として知られています。
銀河超特急999号を走らせることができたのも、普段から多くのSLを運行させていることがひとつの理由でもありました。
ここではそんな大井川鉄道がどのようにして設立され、現在に至るのかお話したいと思います。
大井川鉄道はもともと、林産物の輸送を目的に設立された鉄道で、1927年から1931年にかけて大井川本線が全区間開通しました。
千頭駅から先の井川線は通称南アルプスあぷとラインと呼ばれ、もともとは1935年に大井川電力が発電所とダム建設のために専用軌道を設けたものでした。
そして発電所やダム等の電源開発がひと段落ついたところで、今度は観光路線へと転身し現在に至ります。
接岨峡にかかる高さ100mもの関の沢鉄橋や1.5kmに渡るアプト式区間などが見所となっています。
またかつて工期を短縮するためにトンネル等がコンパクトに造られていたため、トンネルと鉄橋が連続するこの路線の迫力ある趣きが人気を呼んでいます。
煙を上げて走るSL、山岳ではスリルも味わえ、雄大な大井川ダムや接岨峡など多彩に楽しめるのが大井川鉄道の魅力です。
SLの旅に大井川鉄道を選ぶ人も多いと思います。
大井川鉄道では銀河超特急999号を走らせたことでも話題となりましたが、ここのSLは観光列車としても有名です。
大井川鉄道は、たくさんのSLを走らせる状態で保存する「動態保存」している鉄道として知られています。
銀河超特急999号を走らせることができたのも、普段から多くのSLを運行させていることがひとつの理由でもありました。
ここではそんな大井川鉄道がどのようにして設立され、現在に至るのかお話したいと思います。
大井川鉄道はもともと、林産物の輸送を目的に設立された鉄道で、1927年から1931年にかけて大井川本線が全区間開通しました。
千頭駅から先の井川線は通称南アルプスあぷとラインと呼ばれ、もともとは1935年に大井川電力が発電所とダム建設のために専用軌道を設けたものでした。
そして発電所やダム等の電源開発がひと段落ついたところで、今度は観光路線へと転身し現在に至ります。
接岨峡にかかる高さ100mもの関の沢鉄橋や1.5kmに渡るアプト式区間などが見所となっています。
またかつて工期を短縮するためにトンネル等がコンパクトに造られていたため、トンネルと鉄橋が連続するこの路線の迫力ある趣きが人気を呼んでいます。
煙を上げて走るSL、山岳ではスリルも味わえ、雄大な大井川ダムや接岨峡など多彩に楽しめるのが大井川鉄道の魅力です。
Posted by 関 at
23:06
│大井川鉄道の鉄道会社について
2010年04月07日
大井川鉄道SLの旅で見る 車窓の景色
1000年に一度、9がぞろ目で揃う日の2009年9月9日に、静岡県大井川鉄道で銀河超特急999号の特別運行が行なわれました。
車内にも、そして銀河超特急999号が走る沿線にもカメラを持ったファンが詰めかけ、盛んにシャッターを押していたそうです。
この特別列車は新金谷駅から千頭駅を走ったそうですが、普段のSL列車はJR東海と接続している東海道本線金谷駅が始発となります。
しかし大井川鉄道用のホームは短いため、最大で7両もの客車を繋いでいるSL列車は一部がホームにかからないそうです。
さて金谷駅を出発したSL列車は大きくカーブを切った後、大井川に沿って北上します。
やがて新金谷駅に到着しますが、この新金谷駅構内にはバス駐車場があり、団体客はこの駅が起点となります。
また桜や紅葉などのシーズンには1日3往復のSL列車が設定されるため、車庫で煙を上げて待機中のSLを見ることができます。
新金谷駅を出発した列車は千頭駅へと向かうわけですが、途中にある様々な風景も楽しんでください。
神尾駅を通過するときは列車の左側に目をやると、たくさんのたぬきの焼き物が旅の安全を願って並んでいる姿を見ることができます。
また家山駅は春になると満開の桜がとてもきれいな場所です。
車窓にはお茶の段々畑や小さな村が見えてきます。
大井川の川幅が狭くなってくるとSLは川に寄り添い、やがて大井川の対岸へ渡ります。
車窓の右手には、SLの見られる露天風呂として名の知れた川根温泉ふれあいの泉があります。
いくつもの小さな駅を通過し、やがて列車は1時間20分の旅を終えて千頭駅に到着します。
千頭駅の構内は広く、機関車や電車が静態保存されており、SL資料館もあるのでぜひ見学してみたいところです。
車内にも、そして銀河超特急999号が走る沿線にもカメラを持ったファンが詰めかけ、盛んにシャッターを押していたそうです。
この特別列車は新金谷駅から千頭駅を走ったそうですが、普段のSL列車はJR東海と接続している東海道本線金谷駅が始発となります。
しかし大井川鉄道用のホームは短いため、最大で7両もの客車を繋いでいるSL列車は一部がホームにかからないそうです。
さて金谷駅を出発したSL列車は大きくカーブを切った後、大井川に沿って北上します。
やがて新金谷駅に到着しますが、この新金谷駅構内にはバス駐車場があり、団体客はこの駅が起点となります。
また桜や紅葉などのシーズンには1日3往復のSL列車が設定されるため、車庫で煙を上げて待機中のSLを見ることができます。
新金谷駅を出発した列車は千頭駅へと向かうわけですが、途中にある様々な風景も楽しんでください。
神尾駅を通過するときは列車の左側に目をやると、たくさんのたぬきの焼き物が旅の安全を願って並んでいる姿を見ることができます。
また家山駅は春になると満開の桜がとてもきれいな場所です。
車窓にはお茶の段々畑や小さな村が見えてきます。
大井川の川幅が狭くなってくるとSLは川に寄り添い、やがて大井川の対岸へ渡ります。
車窓の右手には、SLの見られる露天風呂として名の知れた川根温泉ふれあいの泉があります。
いくつもの小さな駅を通過し、やがて列車は1時間20分の旅を終えて千頭駅に到着します。
千頭駅の構内は広く、機関車や電車が静態保存されており、SL資料館もあるのでぜひ見学してみたいところです。
2010年04月06日
銀河超特急999号のモデル,C62形蒸気機関車
数あるSLの中でも一番人気があるものと言えば、銀河超特急999号のモデルになったと言われるC62形ではないでしょうか。
C62形は現在、京都府にある梅小路機関車館で保存されていますが、銀河超特急と聞くと2009年に静岡県にある大井川鉄道で走った999号が皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。
大井川鉄道で走った999号はC11形でしたが、ここではSL王者とも言えるC62形機関車についてお話したいと思います。
C62形機関車は全長21.5m、重量とパワーは国鉄最大級の特急用機関車です。
SLファンの間ではシロクニと呼ばれ、不動の人気を誇ってきました。
戦後1948年から1949年にマンモス機関車と呼ばれていた貨物用D52形機関車のボイラーと、急行旅客機C59形機関車の足回りを組み合わせたものがC62形です。
C62形機関車は、その大きなパワーを生かし東海道本線や山陽本線において「つばめ」「はと」や「あさかぜ」「はやぶさ」などよく知られた数々の特急列車の先頭を走ってきました。
また最速の蒸気機関車と言われるC62形は、その17号機が1954年に木曽川の鉄橋上で129km/時を記録しました。
これは日本における蒸気機関車の最高速度記録です。
C62形の2号機は1948年に誕生し、山陽本線に配置後、1950年には大阪の宮原機関区に移動し「つばめ」など大阪と浜松間の特急列車を牽引しました。
その時、デフレクターにつけられたステンレスのつばめマークは、栄光の特急牽引機だった証として輝いています。
C62形は現在、京都府にある梅小路機関車館で保存されていますが、銀河超特急と聞くと2009年に静岡県にある大井川鉄道で走った999号が皆さんの記憶に新しいのではないでしょうか。
大井川鉄道で走った999号はC11形でしたが、ここではSL王者とも言えるC62形機関車についてお話したいと思います。
C62形機関車は全長21.5m、重量とパワーは国鉄最大級の特急用機関車です。
SLファンの間ではシロクニと呼ばれ、不動の人気を誇ってきました。
戦後1948年から1949年にマンモス機関車と呼ばれていた貨物用D52形機関車のボイラーと、急行旅客機C59形機関車の足回りを組み合わせたものがC62形です。
C62形機関車は、その大きなパワーを生かし東海道本線や山陽本線において「つばめ」「はと」や「あさかぜ」「はやぶさ」などよく知られた数々の特急列車の先頭を走ってきました。
また最速の蒸気機関車と言われるC62形は、その17号機が1954年に木曽川の鉄橋上で129km/時を記録しました。
これは日本における蒸気機関車の最高速度記録です。
C62形の2号機は1948年に誕生し、山陽本線に配置後、1950年には大阪の宮原機関区に移動し「つばめ」など大阪と浜松間の特急列車を牽引しました。
その時、デフレクターにつけられたステンレスのつばめマークは、栄光の特急牽引機だった証として輝いています。
2010年04月05日
コンパクトなC56形蒸気機関車
現在、日本の中で運転用蒸気機関車を最も多く保存しているのは大井川鉄道で、計6両を保有しています。
特別列車「銀河超特急999号」として走ったC11形をはじめ、C10形やC12形、C56形が保存されていますが、ここではポニーの愛称で親しまれているC56形蒸気機関車の紹介をしたいと思います。
まずC56形機関車がなぜコンパクトなのかというお話から…
全国各地で鉄道路線の建設が進められた大正時代から昭和初期の頃には、経費をなるべくかけずに多くの路線を建設するため、特にローカル線などでは線路の規格を低くして工事が行なわれました。
その結果、大きさや重量の関係から線路に入れる機関車が限られてしまったため、これらの路線を走る機関車として小回りのきくタンク式C12形が1932年に完成しました。
しかし燃料の積載量が少ないC12形では距離の長い路線を走るには使いづらいため、C12形の多くの部品を同じ設定にしたテンダー機関車C56形が1935年に作られたのです。
この機関車は1軸にかかる重さがわずか11tと、当時ではもっとも軽い機関車となりました。
C56形は転車台のない線区での小運転や操車場での入れ替え作業時などに、バック運転でも前方がよく見えるようにテンダーのサイドを切り取った形をしています。
この形の機関車は160両以上が製造されましたが、戦争が激しさを増していた時代もあり多くが軍の要請でタイやジャワ島、中国へと出されたため、その多くが戦場での犠牲者となってしまいました。
タイから帰還した2両のうち1両は靖国神社の境内で、もう1両は大井川鉄道で保存されています。
C56形160号機については、最後に八ヶ岳山麓の小海線で活躍し、日本の最高地点にある路線を走る小型機関車ということで「高原のポニー」の愛称で親しまれていました。
ちなみに大井川鉄道ではC11形が銀河超特急として走行しましたが、実際のアニメで登場する999号はC62形がモデルとなったと言われています。
C62形についてはまた後ほど紹介したいと思います。
特別列車「銀河超特急999号」として走ったC11形をはじめ、C10形やC12形、C56形が保存されていますが、ここではポニーの愛称で親しまれているC56形蒸気機関車の紹介をしたいと思います。
まずC56形機関車がなぜコンパクトなのかというお話から…
全国各地で鉄道路線の建設が進められた大正時代から昭和初期の頃には、経費をなるべくかけずに多くの路線を建設するため、特にローカル線などでは線路の規格を低くして工事が行なわれました。
その結果、大きさや重量の関係から線路に入れる機関車が限られてしまったため、これらの路線を走る機関車として小回りのきくタンク式C12形が1932年に完成しました。
しかし燃料の積載量が少ないC12形では距離の長い路線を走るには使いづらいため、C12形の多くの部品を同じ設定にしたテンダー機関車C56形が1935年に作られたのです。
この機関車は1軸にかかる重さがわずか11tと、当時ではもっとも軽い機関車となりました。
C56形は転車台のない線区での小運転や操車場での入れ替え作業時などに、バック運転でも前方がよく見えるようにテンダーのサイドを切り取った形をしています。
この形の機関車は160両以上が製造されましたが、戦争が激しさを増していた時代もあり多くが軍の要請でタイやジャワ島、中国へと出されたため、その多くが戦場での犠牲者となってしまいました。
タイから帰還した2両のうち1両は靖国神社の境内で、もう1両は大井川鉄道で保存されています。
C56形160号機については、最後に八ヶ岳山麓の小海線で活躍し、日本の最高地点にある路線を走る小型機関車ということで「高原のポニー」の愛称で親しまれていました。
ちなみに大井川鉄道ではC11形が銀河超特急として走行しましたが、実際のアニメで登場する999号はC62形がモデルとなったと言われています。
C62形についてはまた後ほど紹介したいと思います。
2010年04月04日
貨物用機関車のD51形蒸気機関車
静岡県の大井川鉄道で銀河超特急999号が走ったイベントをご存知でしょうか?
SLファンはもちろんのこと、銀河鉄道999のアニメが好きな人にとってもワクワクするようなイベントであったと思います。
銀河超特急999号は2009年9月9日の「999の日」にちなんで走りましたが、現代においてはこのようにイベントでもない限り蒸気機関車はなかなか見られなくなっていますね。
またSLに乗ることを目的とした大井川鉄道ツアーなどが組まれていることからも、日常ではSLに触れる機会がほとんどないことがわかります。
だからこそ、余計にSLは人々の心を捉えてしまうのかもしれません。
さて蒸気機関車が全国的に多く走っていた頃に、どこへ行ってもよく見られた貨物用機関車にD51形があります。
これは無骨なスタイルのD50形の次に登場した機関車ですが、D51初期型は煙突から給水温め器、砂箱、蒸気だめまでをドームカバーで覆ったスタイルをしていたので、その形から「ナメクジ」と呼ばれていたそうです。
太平洋戦争中には機関車の製作工程を省略するため、ドームカバーの両端を直角にし「カマボコ」と呼ばれたものもあったようです。
このような愛称で呼ばれるのも、多くの人に愛されている蒸気機関車ならではですね。
D51形機関車は本線貨物用機関車として性能的にも完成されたもので、1936年から1945年まで長期に渡って製造が続き、総数1115両が製造されました。
D51形498号機は山陽本線や大阪吹田、常磐線平、北陸本線直江津、羽越本線新津などで使われた後、酒田で廃車となりました。
1988年には大宮工場で復元され、本線に復帰しました。
現在ではJR東日本館内でイベント列車を引いて活躍し、デゴイチヨンキュッパと呼ばれ親しまれています。
東のデゴイチが498なら、西のデゴイチは200号機でしょうか。
こちらは梅小路に保存されています。
SLファンはもちろんのこと、銀河鉄道999のアニメが好きな人にとってもワクワクするようなイベントであったと思います。
銀河超特急999号は2009年9月9日の「999の日」にちなんで走りましたが、現代においてはこのようにイベントでもない限り蒸気機関車はなかなか見られなくなっていますね。
またSLに乗ることを目的とした大井川鉄道ツアーなどが組まれていることからも、日常ではSLに触れる機会がほとんどないことがわかります。
だからこそ、余計にSLは人々の心を捉えてしまうのかもしれません。
さて蒸気機関車が全国的に多く走っていた頃に、どこへ行ってもよく見られた貨物用機関車にD51形があります。
これは無骨なスタイルのD50形の次に登場した機関車ですが、D51初期型は煙突から給水温め器、砂箱、蒸気だめまでをドームカバーで覆ったスタイルをしていたので、その形から「ナメクジ」と呼ばれていたそうです。
太平洋戦争中には機関車の製作工程を省略するため、ドームカバーの両端を直角にし「カマボコ」と呼ばれたものもあったようです。
このような愛称で呼ばれるのも、多くの人に愛されている蒸気機関車ならではですね。
D51形機関車は本線貨物用機関車として性能的にも完成されたもので、1936年から1945年まで長期に渡って製造が続き、総数1115両が製造されました。
D51形498号機は山陽本線や大阪吹田、常磐線平、北陸本線直江津、羽越本線新津などで使われた後、酒田で廃車となりました。
1988年には大宮工場で復元され、本線に復帰しました。
現在ではJR東日本館内でイベント列車を引いて活躍し、デゴイチヨンキュッパと呼ばれ親しまれています。
東のデゴイチが498なら、西のデゴイチは200号機でしょうか。
こちらは梅小路に保存されています。
2010年04月03日
C11形SL蒸気機関車の銀河超特急999号
山々が色付く秋には、鉄道旅行というのも趣き深いものです。
大井川鉄道のように普段から蒸気機関車を走らせているところもあるので、いつもは車派の人もたまにはSLに乗って出かけてみるのもよいかもしれません。
2009年9月には、蒸気機関車復活30年を記念して大井川鉄道で銀河超特急999号が走りました。
アニメの銀河鉄道に憧れて、本物さながらの銀河超特急999号に乗車するファン、沿線で写真に納めるファンと多くの人が集まったようです。
この時、銀河超特急として走行したのがC11形SLです。
ここでは北海道で活躍しているC11形171号機と207号機について紹介したいと思います。
これらの機関車は1932年、大都市近郊地域を走るローカル線区間用や快速列車として誕生しました。
この機関車の特徴として、1C2というタンク機関車に適した車軸配置や、後部に控える石炭庫の左右を切り取ってバック運転する時の視界を良くした点が挙げられます。
製造台数は381両にも及び、シーチョンチョンという愛称で呼ばれ全国のローカル線で活躍してきました。
171号機は1940年に製造され名古屋近郊で働いた後、1952年には北海道に渡り、釧路の標津線で終焉を迎えました。
その後は標茶町の公園に展示されていましたが、1999年に苗穂工場で復元され、現在ではSLすずらん号として運転されています。
留萌本線を舞台としたNHKドラマにも出演したことがありますが、皆さんご存知ですか?
207号機は1941年に完成、1974年に廃車となるまで長万部機関区などで働きました。
こちらも苗穂工場で2000年に復元され、函館本線でSLニセコ号として活躍しています。
かつてカーブの多い路線を走っていたためヘッドライトが2個ついている「2つ目」が外観の特徴となっています。
ここでは北海道で走っているC11形について紹介しましたが、C11形は大きさが手頃なのと運転のし易さで人気があり、大井川鉄道や真岡鉄道など全国で活躍しています。
大井川鉄道のように普段から蒸気機関車を走らせているところもあるので、いつもは車派の人もたまにはSLに乗って出かけてみるのもよいかもしれません。
2009年9月には、蒸気機関車復活30年を記念して大井川鉄道で銀河超特急999号が走りました。
アニメの銀河鉄道に憧れて、本物さながらの銀河超特急999号に乗車するファン、沿線で写真に納めるファンと多くの人が集まったようです。
この時、銀河超特急として走行したのがC11形SLです。
ここでは北海道で活躍しているC11形171号機と207号機について紹介したいと思います。
これらの機関車は1932年、大都市近郊地域を走るローカル線区間用や快速列車として誕生しました。
この機関車の特徴として、1C2というタンク機関車に適した車軸配置や、後部に控える石炭庫の左右を切り取ってバック運転する時の視界を良くした点が挙げられます。
製造台数は381両にも及び、シーチョンチョンという愛称で呼ばれ全国のローカル線で活躍してきました。
171号機は1940年に製造され名古屋近郊で働いた後、1952年には北海道に渡り、釧路の標津線で終焉を迎えました。
その後は標茶町の公園に展示されていましたが、1999年に苗穂工場で復元され、現在ではSLすずらん号として運転されています。
留萌本線を舞台としたNHKドラマにも出演したことがありますが、皆さんご存知ですか?
207号機は1941年に完成、1974年に廃車となるまで長万部機関区などで働きました。
こちらも苗穂工場で2000年に復元され、函館本線でSLニセコ号として活躍しています。
かつてカーブの多い路線を走っていたためヘッドライトが2個ついている「2つ目」が外観の特徴となっています。
ここでは北海道で走っているC11形について紹介しましたが、C11形は大きさが手頃なのと運転のし易さで人気があり、大井川鉄道や真岡鉄道など全国で活躍しています。
2010年04月02日
蒸気機関車の運転手順
アニメの世界を走る銀河超特急999号は自動運転になっていて、顔の見えない謎の車掌さんが客車に度々登場します。
しかし2009年9月、大井川鉄道で走った銀河超特急999号は当然ながら機関士さんの運転で走りました。
あのレトロな蒸気機関車の運転は、さぞかし難しいことでしょう。
蒸気機関車の運転にはどんな手順でどのような操作が行なわれているのでしょうか。
大井川鉄道の機関士さんのお話を例に、順に説明したいと思います。
前にお話したように、蒸気機関車は多くの人の手によって時間をかけて発車準備が行なわれます。
火室内では火力がぐんぐん上がり、ボイラーの水が沸騰して蒸気が出来上がります。
圧力計のメーターもどんどん上がりいよいよ機関車に命が吹き込まれるのです。
各点検を済ませたら、信号を確認して出発です。
1.ブレーキハンドルをゆるめ、レギュレーターハンドルを手前に引くと、ゆっくりと機関車が動き出します。
ブレーキは上下にあり、上は機関車のみにかかり下は列車全体にかかるブレーキです。
レギュレーターハンドルは自動車で言うとアクセルに当たる部分です。
左手は砂まきレバー(車輪が空回りしないため)を握っておきます。
2.機関車が動き出したら、逆転ハンドルを操作します。
逆転ハンドルは機関車の走る方向を変えるだけでなく、勾配や速度などによって調整するギアのような役割も持っています。
3.停車時間が長い場合はシリンダーに送られた蒸気が冷えてしまったり、蒸気が水滴になってシリンダーに溜まったりするため、足元のドレインハンドルを操作してこれらを排出します。
出発時に機関車の下からシューッと蒸気が噴き出すのを見たことがあるかもしれませんが、この操作を行なっているためです。
4.機関車が順調に動き出した後も、常に火力を調整して蒸気の圧力を一定に保っておく必要があります。
そのため圧力計を確認しながら石炭を焚いたりボイラーに水を送ったり、といった操作が欠かせません。
経験豊富な機関士と機関助士のチームワークがあってこそ、安全に順調に蒸気機関車は走ることができるのです。
しかし2009年9月、大井川鉄道で走った銀河超特急999号は当然ながら機関士さんの運転で走りました。
あのレトロな蒸気機関車の運転は、さぞかし難しいことでしょう。
蒸気機関車の運転にはどんな手順でどのような操作が行なわれているのでしょうか。
大井川鉄道の機関士さんのお話を例に、順に説明したいと思います。
前にお話したように、蒸気機関車は多くの人の手によって時間をかけて発車準備が行なわれます。
火室内では火力がぐんぐん上がり、ボイラーの水が沸騰して蒸気が出来上がります。
圧力計のメーターもどんどん上がりいよいよ機関車に命が吹き込まれるのです。
各点検を済ませたら、信号を確認して出発です。
1.ブレーキハンドルをゆるめ、レギュレーターハンドルを手前に引くと、ゆっくりと機関車が動き出します。
ブレーキは上下にあり、上は機関車のみにかかり下は列車全体にかかるブレーキです。
レギュレーターハンドルは自動車で言うとアクセルに当たる部分です。
左手は砂まきレバー(車輪が空回りしないため)を握っておきます。
2.機関車が動き出したら、逆転ハンドルを操作します。
逆転ハンドルは機関車の走る方向を変えるだけでなく、勾配や速度などによって調整するギアのような役割も持っています。
3.停車時間が長い場合はシリンダーに送られた蒸気が冷えてしまったり、蒸気が水滴になってシリンダーに溜まったりするため、足元のドレインハンドルを操作してこれらを排出します。
出発時に機関車の下からシューッと蒸気が噴き出すのを見たことがあるかもしれませんが、この操作を行なっているためです。
4.機関車が順調に動き出した後も、常に火力を調整して蒸気の圧力を一定に保っておく必要があります。
そのため圧力計を確認しながら石炭を焚いたりボイラーに水を送ったり、といった操作が欠かせません。
経験豊富な機関士と機関助士のチームワークがあってこそ、安全に順調に蒸気機関車は走ることができるのです。
Posted by 関 at
23:39
│蒸気機関車が走るまで