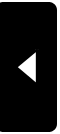2010年04月02日
発車前準備の蒸気機関車
蒸気機関車が煙を上げて走る姿にどことなく哀愁を感じる人は少なくないと思います。
そんなSLに憧れて、全国の蒸気機関車が走っている路線を旅している人も多いことでしょう。
SLが走行していることで有名なのは大井川鉄道ではないでしょうか。
2009年の秋にも銀河超特急999号がこの大井川鉄道を走ったことでニュースになっていました。
特に銀河超特急999号ということで、SLファンのみならず、アニメファンも多く集ったそうです。
さて蒸気機関車が走るためには自分自身でエネルギーを作り出さなければならないことは知られていることと思います。
架線からエネルギーをもらいながら走る電気機関車とは異なり、蒸気機関車は走るための準備に多くの人でと長い時間を要します。
ここでは蒸気機関車が走る前に、どのような準備が必要なのかを順に説明したいと思います。
1.燃料となる石炭を積み込みます。
現在ではフォークリフトを使って行ないます。
2.ホースで機関車に水を入れます。
本格的な給水設備がないところでは、細いホースを使って長い時間かけて給水作業を行ないます。
3.車輪の空回りを防ぐための砂を天日干しします。
雨の日は車輪の空転を防ぐために機関士の操作で線路に砂をまくのですが、この砂は乾いていないと使用できないのです。
ちなみに砂の入っているドームは機関車のボイラーの上にあります。
4.ロッドの汚れを落として磨いたり、油を差して滑らかに動くようにしておきます。
5.運転時間の3時間前にボイラーに点火します。
冬の寒い時期は、3時間以上前から点火しておきます。
まずボロ布に火をつけて、木材で火室内の火が燃え上がるのを確認後、石炭を焚きます。
6.動輪やロッドをハンマーで叩いてチェックするなど、機関士によって運転前の最後の点検が行なわれます。
運転室においてもブレーキハンドルの取り付けや各部の点検が行なわれます。
そんなSLに憧れて、全国の蒸気機関車が走っている路線を旅している人も多いことでしょう。
SLが走行していることで有名なのは大井川鉄道ではないでしょうか。
2009年の秋にも銀河超特急999号がこの大井川鉄道を走ったことでニュースになっていました。
特に銀河超特急999号ということで、SLファンのみならず、アニメファンも多く集ったそうです。
さて蒸気機関車が走るためには自分自身でエネルギーを作り出さなければならないことは知られていることと思います。
架線からエネルギーをもらいながら走る電気機関車とは異なり、蒸気機関車は走るための準備に多くの人でと長い時間を要します。
ここでは蒸気機関車が走る前に、どのような準備が必要なのかを順に説明したいと思います。
1.燃料となる石炭を積み込みます。
現在ではフォークリフトを使って行ないます。
2.ホースで機関車に水を入れます。
本格的な給水設備がないところでは、細いホースを使って長い時間かけて給水作業を行ないます。
3.車輪の空回りを防ぐための砂を天日干しします。
雨の日は車輪の空転を防ぐために機関士の操作で線路に砂をまくのですが、この砂は乾いていないと使用できないのです。
ちなみに砂の入っているドームは機関車のボイラーの上にあります。
4.ロッドの汚れを落として磨いたり、油を差して滑らかに動くようにしておきます。
5.運転時間の3時間前にボイラーに点火します。
冬の寒い時期は、3時間以上前から点火しておきます。
まずボロ布に火をつけて、木材で火室内の火が燃え上がるのを確認後、石炭を焚きます。
6.動輪やロッドをハンマーで叩いてチェックするなど、機関士によって運転前の最後の点検が行なわれます。
運転室においてもブレーキハンドルの取り付けや各部の点検が行なわれます。
Posted by 関 at
23:38
│蒸気機関車が走るまで
2010年04月02日
世界共通の蒸気機関車の愛称
子どもに人気のあるキャラクターのひとつに機関車トーマスがあります。
機関車というのは、大人にとってはどこか懐かしい、そして子どもにとっては新鮮な乗り物であるような気がします。
アニメの世界でも蒸気機関車が登場します。
有名な銀河鉄道999に登場する銀河超特急999号がそのひとつで、2009年9月、大井川鉄道での銀河超特急999号お披露目時には多くの鉄道ファン、アニメファンが集まったそうです。
大井川鉄道では普段から蒸気機関車が走っているので、本物の蒸気機関車が走る姿を見たことのない人は、一度訪れて見るのもよいですね。
ところで、さまざまな形のある蒸気機関車には国によっていろいろな呼び方があることはご存知ですか?
日本やドイツの国鉄では軸数を数字で、動輪の数をアルファベットで表示するため2C2や1D1と表されます。
フランスにおいては動輪の数も数字で表示されるため232や141と表され、それがそのまま機関車の形式番号とされています。
アメリカでは左右一対の車輪数による記号を使い464や282と表示され、これはホワイト式と呼ばれています。
しかしアメリカでは、それらの車軸配置を初めに使用した鉄道会社のある地域名が愛称としてつけられ、ホワイト式よりも愛称で呼ばれる方が一般的です。
例えば464はハドソン、282はミカド、462はパシフィック、などです。
ミカドと聞いて、何だか和風な愛称だと感じた人もいるのではないでしょうか。
実は、明治時代に282車軸配置の機関車の注文が日本からアメリカのメーカーに入り、帝の国の機関車という意味から「ミカド」という愛称がつけられたそうです。
これらの愛称は、多くのSLファンの間では世界共通で使われているそうです。
機関車というのは、大人にとってはどこか懐かしい、そして子どもにとっては新鮮な乗り物であるような気がします。
アニメの世界でも蒸気機関車が登場します。
有名な銀河鉄道999に登場する銀河超特急999号がそのひとつで、2009年9月、大井川鉄道での銀河超特急999号お披露目時には多くの鉄道ファン、アニメファンが集まったそうです。
大井川鉄道では普段から蒸気機関車が走っているので、本物の蒸気機関車が走る姿を見たことのない人は、一度訪れて見るのもよいですね。
ところで、さまざまな形のある蒸気機関車には国によっていろいろな呼び方があることはご存知ですか?
日本やドイツの国鉄では軸数を数字で、動輪の数をアルファベットで表示するため2C2や1D1と表されます。
フランスにおいては動輪の数も数字で表示されるため232や141と表され、それがそのまま機関車の形式番号とされています。
アメリカでは左右一対の車輪数による記号を使い464や282と表示され、これはホワイト式と呼ばれています。
しかしアメリカでは、それらの車軸配置を初めに使用した鉄道会社のある地域名が愛称としてつけられ、ホワイト式よりも愛称で呼ばれる方が一般的です。
例えば464はハドソン、282はミカド、462はパシフィック、などです。
ミカドと聞いて、何だか和風な愛称だと感じた人もいるのではないでしょうか。
実は、明治時代に282車軸配置の機関車の注文が日本からアメリカのメーカーに入り、帝の国の機関車という意味から「ミカド」という愛称がつけられたそうです。
これらの愛称は、多くのSLファンの間では世界共通で使われているそうです。
2010年04月02日
蒸気機関車がモデルの銀河超特急999号
銀河超特急999号が大井川鉄道を走ったというニュースは記憶に新しいところではないでしょうか。
多くの蒸気機関車(SL)ファンだけでなく、アニメファンにとっても興味深いイベントであったと思います。
さて、銀河超特急999号のモデルとなった蒸気機関車がC62という実在するものであったことはご存知でしょうか。
大井川鉄道で走った999号はC11でしたが、ここではC62とかC11と言った蒸気機関車の形式の読み方について説明したいと思います。
蒸気機関車は、走るためのエネルギーを自分で作る必要があります。
エネルギーとなる蒸気を作り出すための石炭と水を積んで走るのですが、ローカル線などの短距離用小型機関車は積む燃料も少なくて済むため、ボイラーの横に水タンク、運転室の後ろに石炭庫をつけたスタイルのタンク機関車と呼ばれています。
一方で長距離を走る大型機関車は大量の石炭と水が必要なため、機関車の後ろにテンダーと呼ばれる炭水車を連結しており、テンダー機関車と呼ばれています。
機関車は動軸の数をアルファベットで表現し、動輪が3つのものがC、4つのものがD、5つのものがEとなっています。
さらにタンク機関車はC10やC11のように、アルファベットの後に10~の番号が付けられます。
テンダー機関車ではD51やC57のように50~の番号が付けられています。
タンク機関車はバック運転も得意なので入れ替えにも便利ですが、燃料を満載している時と空になった時とで機関車の重さが変わってしまい、性能が一定しにくいという難点もあります。
テンダー機関車ではたくさんの燃料を積むため炭水車を引いているし、全体の長さにも無駄が出てしまうなどの欠点があります。
多くの蒸気機関車(SL)ファンだけでなく、アニメファンにとっても興味深いイベントであったと思います。
さて、銀河超特急999号のモデルとなった蒸気機関車がC62という実在するものであったことはご存知でしょうか。
大井川鉄道で走った999号はC11でしたが、ここではC62とかC11と言った蒸気機関車の形式の読み方について説明したいと思います。
蒸気機関車は、走るためのエネルギーを自分で作る必要があります。
エネルギーとなる蒸気を作り出すための石炭と水を積んで走るのですが、ローカル線などの短距離用小型機関車は積む燃料も少なくて済むため、ボイラーの横に水タンク、運転室の後ろに石炭庫をつけたスタイルのタンク機関車と呼ばれています。
一方で長距離を走る大型機関車は大量の石炭と水が必要なため、機関車の後ろにテンダーと呼ばれる炭水車を連結しており、テンダー機関車と呼ばれています。
機関車は動軸の数をアルファベットで表現し、動輪が3つのものがC、4つのものがD、5つのものがEとなっています。
さらにタンク機関車はC10やC11のように、アルファベットの後に10~の番号が付けられます。
テンダー機関車ではD51やC57のように50~の番号が付けられています。
タンク機関車はバック運転も得意なので入れ替えにも便利ですが、燃料を満載している時と空になった時とで機関車の重さが変わってしまい、性能が一定しにくいという難点もあります。
テンダー機関車ではたくさんの燃料を積むため炭水車を引いているし、全体の長さにも無駄が出てしまうなどの欠点があります。
Posted by 関 at
23:36
│銀河鉄道999号のモデル
2010年04月02日
静岡県,大井川鉄道を走る銀河超特急999号
2009年9月9日、大井川鉄道を銀河超特急999号が走ったというニュースは、鉄道ファン、アニメファンでなくても聞いたことがあるでしょう。
日付に9が揃う、まさにスリーナインの日、この日は平日にも関わらずカメラを持った多くのファンが沿線に詰め掛けたようです。
この企画は奈良市にある鉄道部品店のよるもので、蒸気機関車が復活して30年、そして「銀河鉄道999」第1作が公開されて30年という節目を記念してのものでした。
鉄道ファンのみならず、昔から銀河鉄道999のファンだった人にも物語の中にいる気分を味わってほしい、という思いで計画されたようです。
当初の計画では、銀河超特急999号は大阪と津和野の間で、9月9日の深夜に出発し3日間かけて往復する予定が立てられていました。
その計画で乗客を募集し、既に60人程が申し込んでいたのですが、JR側から「沿線が混乱するのを避けるため、999号のヘッドマークは外せないか」との要望があり、それを呑めない企画側は大阪発の計画を断念しました。
その後、蒸気機関車を定期運行させている大井川鉄道で銀河超特急が運行できることとなり、この企画が実現しました。
深夜に走る、という計画は実行されなかったものの、乗客が自分で定期券に記名して乗車したり停車駅では作品に出てくる駅名が使われたりと、原作さながらの演出がされました。
列車内には顔の見えない車掌やメーテルも登場し、銀河超特急での旅を終えた乗客は大満足の表情をしていたそうです。
ちなみ運行後の即売会で販売された「999」のヘッドマークは79万9999円だそうです。
日付に9が揃う、まさにスリーナインの日、この日は平日にも関わらずカメラを持った多くのファンが沿線に詰め掛けたようです。
この企画は奈良市にある鉄道部品店のよるもので、蒸気機関車が復活して30年、そして「銀河鉄道999」第1作が公開されて30年という節目を記念してのものでした。
鉄道ファンのみならず、昔から銀河鉄道999のファンだった人にも物語の中にいる気分を味わってほしい、という思いで計画されたようです。
当初の計画では、銀河超特急999号は大阪と津和野の間で、9月9日の深夜に出発し3日間かけて往復する予定が立てられていました。
その計画で乗客を募集し、既に60人程が申し込んでいたのですが、JR側から「沿線が混乱するのを避けるため、999号のヘッドマークは外せないか」との要望があり、それを呑めない企画側は大阪発の計画を断念しました。
その後、蒸気機関車を定期運行させている大井川鉄道で銀河超特急が運行できることとなり、この企画が実現しました。
深夜に走る、という計画は実行されなかったものの、乗客が自分で定期券に記名して乗車したり停車駅では作品に出てくる駅名が使われたりと、原作さながらの演出がされました。
列車内には顔の見えない車掌やメーテルも登場し、銀河超特急での旅を終えた乗客は大満足の表情をしていたそうです。
ちなみ運行後の即売会で販売された「999」のヘッドマークは79万9999円だそうです。
Posted by 関 at
23:34
│アニメの銀河鉄道999号について